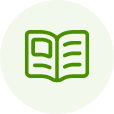大学で障害学生の支援に携わる玄嶋さん。専門職ではない立場だからこそ、学びたいと思った“ユニバーサルマナー”。日々の支援にどう活かされていくのか、検定を通じた気づきと想いを伺いました。
現在のお仕事について教えてください。
大学の障がい学生支援室で、派遣職員として勤務しています。視覚障害のある学生さんの誘導や、点字教科書の製本・データ化、車いすを利用されている学生さんの移動補助、音声教材への対応、また精神障害や発達障害のある学生さんへの学習・環境面でのサポート調整など、幅広い業務に携わっています。
学生さんの困りごとに対して、専門のコーディネーターと連携しながら支援を行っており、私はその補助スタッフという立場です。「大学で学ぶ誰もが、学びたいことを学ぶ」。微力ながらその力になれればと思っています。現在は“学生サポーター”という、「自分も一緒にサポート活動をやりたい!」と手を挙げてくれた学生さんの指導も担当しています。
ユニバーサルマナー検定の受講を決めた背景をお聞かせください。
実は2年前、同じ職場の正職員さんがこの検定を受講されていて、そこで初めて存在を知りました。「いつか自分も受けてみたい」と思っていたのですが、障害のある学生さんと接する中で、「もっと理解を深めたい」「自信を持って対応したい」という思いが強くなり、今回ようやく受講を決めました。
周囲には、教員免許や公認心理師の資格を持つ方がほとんどで、そうした中で働くにあたり、「専門職ではないけど、私なりに知識を深めて寄り添う力を高めていきたい」と思ったのも、受講の大きな理由です。

実際に検定を受講してみて、印象に残っていることはありますか?
「相手の気持ちに寄り添うことが何より大事」という学びが、とても心に残りました。よかれと思って行った行動でも、相手にとっては負担になることもある。それを改めて認識できたのは大きかったです。
また、「声をかけてから行動する」「見守ることもサポートになる」という視点は、今まで曖昧だった自分の行動を肯定できるきっかけにもなりました。たとえば、視覚障害のある学生さんをお手洗いにご案内したときも、どこで待機すればよいのか悩んでいたのですが、今日の学びで「あの対応でよかったんだ」と確認でき、ほっとしました。
実技体験ではどのような気づきがありましたか?
視覚障害者のサポートは実際の業務で経験がある分、日々の対応を振り返る良い機会になりました。
一方、高齢者疑似体験は初めての経験で、本当に驚きました。装具をつけて体を動かしたとき、「これで毎日移動されているなんて、そりゃ疲れる…」と実感しましたし、膝が曲がらず、首も上がらない中で生活する不自由さに驚きました。普段自分が思っている “当たり前のこと”が、誰かの当たり前と必ずしもイコールではない、ということにも気づかされました。
今後、この学びをどのように活かしていきたいですか?
 まずは、職場の中でまだ受講していない方にも、ぜひユニバーサルマナー検定の受講をおすすめしたいです。私自身、職場の正職員さんが受講されたことでこの検定を知ることができました。だからこそ今度は、私からもまだ知らない誰かに伝えていきたい、そんなふうに感じる学びでした。
まずは、職場の中でまだ受講していない方にも、ぜひユニバーサルマナー検定の受講をおすすめしたいです。私自身、職場の正職員さんが受講されたことでこの検定を知ることができました。だからこそ今度は、私からもまだ知らない誰かに伝えていきたい、そんなふうに感じる学びでした。
また、私のように専門職ではない立場の人でも、きちんと理解し、関わっていけるようになる。その第一歩として、多くの方に経験してほしいと思います。
さらに、これまで障害のある方と関わる機会がなかった人にも、この検定を知ってもらえたらうれしいです。「自分には関係ない」と思っていたことが、「ちょっと声をかけてみようかな」「気にかけてみようかな」という気づきにつながるかもしれません。そんな小さなきっかけの積み重ねが、少しずつ社会をやわらかく、やさしくしていくと思っています。
ユニバーサルマナー検定をご受講いただき、ありがとうございました。